
縄文ポシェットさん、今年もいろいろありがとう!お歳暮あげるよ。
ありがとう!あれ・・?お歳暮って昔からあったの?何を贈ってどんな意味があったの?

この記事ではお歳暮のルーツや変化、贈り物の歴史や意味を解説します。
古い慣習として受け継がれつつも、必要ないという意見もあるお歳暮ですが、見方が少し変わるかもしれませんよ。
目次
お歳暮のルーツと変化
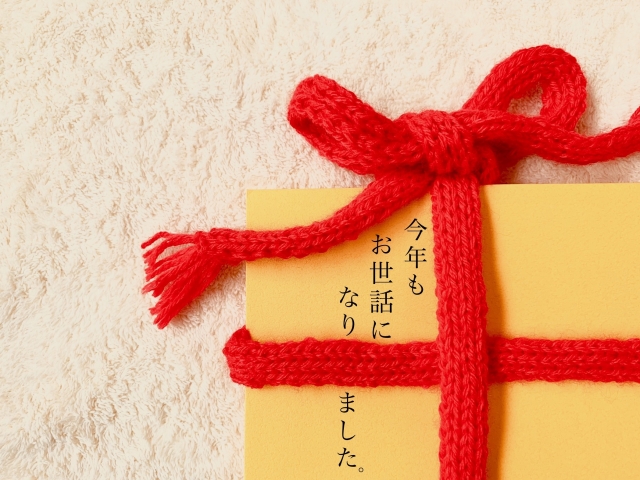
お歳暮のルーツは、中国の行事と日本で古くから行われていた風習があわさったと言われています。
中国では、道教の行事で神様のお祭りにお供え物をする習慣がありました。
日本では、新しい年の神様「年神様」や先祖の御霊にお供え物を捧げ、年の暮れに実家や本家などの親類縁者に手渡しで持っていくという風習があり、これらが混ざり合ったのがはじまりといわれています。
江戸時代になると、武士が目上の人に品物を贈ったり、商人が決算の時期(=お中元やお歳暮の時期)にお得意様に配り物をするようになります。
明治時代以降には、都市に住む人が増え、デパートができて、お歳暮商品の開発や販売促進が行われました。
また目上の人や権力者に気に入られる、企業の取引を円滑にする目的の使い方もされるようになります。

近しい間柄でのやりとりがだんだん複雑化していったんだね。
そして近年では、コンプライアンスの関係で企業同士のお歳暮を禁止する会社もあったり、煩雑さを避けるため、相談して廃止するというお家もあるのだとか。
それでもなお、その年にお世話になった方への感謝を伝えるギフトとして、お歳暮は存続しています。
簡単にまとめると、神様やご先祖さまへのお供え物を、親類縁者に配り、福を分けてもらい先祖を供養するための贈り物から、お世話になった人へ日頃の感謝を伝えるギフトに変化したのですね。
お歳暮を贈るときは、日頃の感謝に加えて、相手の幸せを願うから、そこんとこに昔のエッセンスが残っているのかもね。

「のし」の正体は、〇〇〇!?
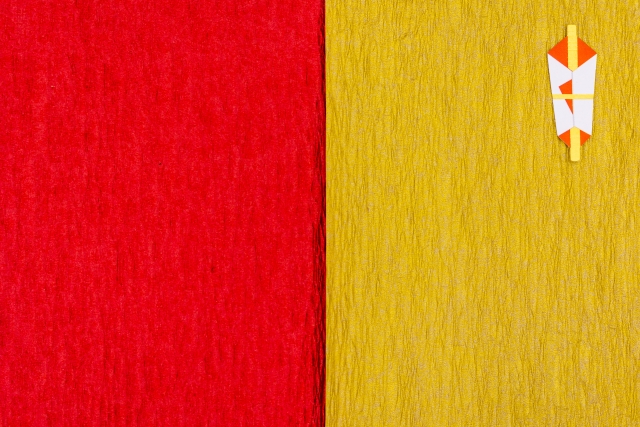
御歳暮には必ずといっていいほどついてくる「のし」。
「のし」はもともと何だったのかご存知でしょうか?
・・・

答えは「のし(熨斗)とは、もともとアワビの肉を薄く剥いで乾かしたものだよ」
え?あのおしゃれなマークが、アワビなの?
みんな知ってた?


のし(熨斗)は、現在でも伊勢神宮で供物として神様のところへ運ばれています。
かつて人々の贈答の際に、本物のアワビののし(熨斗)が添えられていた時代もあったそうです。
有名な民俗学者・柳田国男がいうには、熨斗をつけてはならないときが3つあって、「贈り物が魚鳥のとき」「鰹節のような動物質の食料がすでに贈り物の中身にあるとき」、「精進の日」でした。
贈り物には原則として熨斗や鰹節のような生臭ものを添える慣習があったということがわかります。

精進の日というのは、葬式や法事などの生臭物を食べてはいけない日のことだよ。
昆布・のり・するめといった海藻や軟体動物も生臭物に含まれ、よく贈られたそうです。
現代でも、昆布やのりは日持ちするからって贈る人も多いけど、もともとはこちらが理由だったのかもね。

宴会と水産物と神様

あなたは、宴会はお好きですか?
宴会は太古の昔から行われており、参加者同士の結びつきを強くするという目的もありましたが、神様と一緒に飲食するという意味もありました。

神様と飲食するってどういうこと?
それに、お歳暮やのしになんの関係があるのさ?
宴会においても、「のし(熨斗)=アワビ」が重要な海産物の代表的存在でした。
前述の伊勢神宮のように、海産物は神に対しての供物にもなっており、各地の漁民は供祭物を捧げることで神社から漁業特権を認められます。
神に捧げられた物は、直会(なおらい)と呼ばれる宴会で、参加者にも分け与えられていました。つまり、神様からのおすそ分け的な「神と人が共食」するかたちになっていたのです。
この宴会の目的は、神と人、そして人間同士が繋がりをもつために同じものを食べるということでした。

神様と人が飲食をともにすることを「神人共食」というよ。神様と一緒に同じものを食べることで、神様との結びつきも強くなると考えられていたんだ。
室町時代・節句と贈り物

さて、ここから室町時代の話に入ります。
なぜ、室町時代を取り上げるのか?というと、
室町時代には多くの年中行事や故実書(昔の作法や儀礼についての書)が作られ、日記も豊富なので、具体的に分かりやすいから。また、一説にはお歳暮は室町時代から定着したとも言われています。
今回のテーマのお歳暮に限らず室町時代は、身分にもよりますが、かなりの頻度で贈り物がされる社会でした。
年中行事のうち、代表的なものが「五節供」です。
「五節供」(現代では「五節句」)とは、元旦、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日で、9月9日の重陽を除いては、現代でも行事として残っていますね。
五節句以外に「節」がつく日もいくつかあって、「節分」や「お節料理」など、季節の変わり目をあらわす節目に行事がおこなわれることが多く、その度に物のやりとりがおこなわれました。
年中行事では、正月がもっとも重要とされ、公家・大名・幕府直属のお供衆などが幕府にあいさつをしに来て、贈り物の交換をしました。

節目ってけっこういっぱいあるから、昔の人ってもしや忙しかったんじゃない?
室町時代・歳末の贈り物(お歳暮)
「美物」ってなに?
現代のお歳暮のように、室町時代にも歳末に贈り物を目上の人に献上する通例がありました。
室町時代の日記によく登場する言葉に「美物(びぶつ)」があります。
「美物」とは、おいしいたべもののことで、おもに魚鳥類をさしました。
歳末には、大名から将軍(幕府)への美物献上と、大みそかに将軍から、院・天皇へ美物を贈る慣例がありました。
将軍から天皇へは大みそかの夜が原則で、年越しの意味があったそうです。

民俗事例では、年越しの節といって、大晦日の夜に、尻尾と頭のついた魚をのせた、正式な食事を食べる風習があるんだって。
大名から将軍へ
室町幕府の年中行事を詳細に記した書である『年中恒例記』。
この書には、大みそかに有力な守護大名たちが、将軍に贈り物の目録を披露することが書かれています。
『殿中申次記』には、その目録を披露する順番が書かれています。
延徳年(1491年)に記された名前をあげると・・・
目録披露の順番
斯波氏 細川氏(右京大夫) 畠山氏 一色氏 細川氏(讃岐守) 山名氏 赤松氏 京極氏(大膳大夫) 大内氏 京極氏(治部少輔)
大名から将軍への献上品
北畠氏・歳暮御礼として「海老10籠」を献上

北畠氏は伊勢の守護なので、伊勢エビですね。
伊勢神宮は室町将軍が参詣するほどの特別な場所だったことや、海老の腰が曲がった姿が長寿を連想させること、姿の特異性と赤という目立つ色も関係して、
海老は特別な献上品にふさわしかったのでしょう。
細川氏・「美物と炭」を献上

細川氏の所領である丹波は炭の産地で、「丹炭」「丹波炭」と呼ばれ京都で人気だったそうです。
炭は「歳末節料」といって、正月の準備にあてるための「薪や炭」を代表とする物資で、荘園から徴発されるもので、守護は庄民(荘園にすむ人びと。庶民)たちの贈与という名目で手に入れていたそうです。

スネ夫(細川氏)がのび太(庄民)に「その漫画を俺にプレゼントしろ」と言って、無理やりもらってから、ジャイアン(将軍)に献上するみたいな感じかな?
朝倉氏・歳暮美物として「越前の名産品」を献上

12月29日、朝倉氏景が将軍義尚に「白鳥・鷹(タカ)・タラ・タイ・塩引・カニ」を献上しました。

タラと越前蟹(ズワイガニ)は今も越前の名産品だもんね〜
美物を贈ることは負担でありましたが、高い家格をあらわす名誉だったので、みんながんばったのですね。
守護大名たちは、国から運ばせるか、京で購入するかの2通りで美物を調達していました。
将軍から天皇・院への献上品

永享2年以降、大みそかには 将軍・足利義教から貞成親王へ美物が贈られました。
以下のような内容です。
将軍から親王へ贈られた魚介類
将軍から親王へ贈られた魚介類
鯉、鯛、鱒(ます)、鰆(さわら)、鱈(たら)、カニ、クラゲ、カキ、海老、エイ、くるくる
現代ではあまり食べられませんが、鯉(コイ)は古代以来最上の魚とされています。
くるくるとは「来々」と書き、タラのはらわたのことで、珍重されていたらしいものの、実態は不明という謎の食べ物です。
将軍から親王へ贈られた鳥類

将軍から親王に贈られた鳥類
鵠(くぐい・白鳥ともいう)、菱食(ひしくい)、雁(かり)、雉(きじ)、水鳥、うさぎ
雉は古代から天皇が行う狩猟の獲物で、つがいで木の枝につけるのが通例でした。
鷹狩りの獲物である鵠・菱食・雁はこの順でランク付けがなされていました。
うさぎは鳥扱いです。
豪華だな、さすが将軍だな~とおもいますよね?
でも、これらの将軍から親王へ贈られた美物は、大名からの流用品であったと言われています。

現代の感覚でいったら失礼だなってなるけど、室町時代はそうでもなかったのかなぁ?
より権威の高い人へバトンみたいに渡っていっただけなのかもね。
現代みたいにお店があるわけでもないし、すべての物が誰かによって用意されたものだからね。

おわりに
以上、御歳暮の由来やのし(熨斗)のもともとの姿、宴会とのつながり、そして室町時代にさかのぼって、歳末の贈り物のやりとりについてみてきました。
お歳暮の歴史まとめ
- お歳暮は、神様やご先祖さまへのお供え物を、親類縁者に配り、福を分けてもらい先祖を供養するための贈り物から、お世話になった人へ日頃の感謝を伝えるギフトに変化した
- のし(熨斗)のもともとの姿はアワビ。同じ物を食べてつながりをもつ意味もあった
- 宴会は、神様と人、参加者同士がつながるための「神人共食」の場だった
- 室町時代のお歳暮ともいえる歳末の贈り物は、在地(生産地)→守護→将軍→天皇や院と美物が献上されていった


